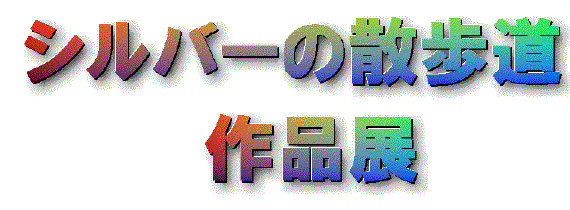 |
mori�����V���o�[���Q�T�N�Ԃɍ쐬�������U�[�N���t�g��i�̂g�o�W�����ł��B
���U�[�N���t�g��i���Љ�Ȃ��烌�U�[�J�[�r���O�͗l�̍����A�l�[������̓�����A
�v�̐����A��D���̕��@�A��������@�Ȃǂ̏Љ������܂��B
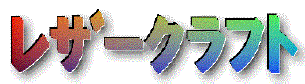 |
�o�W���͖�U�O�_

|
��i�` |
�ŏ��̍�i |
�|�V�F�b�g |
|
��D�� |
�J�[�r���O�i����j |
���U�[�N���t�g����
�s�̖��S�V�w���ɂ������_�C�G�[�i�����\��N���ɕX�j�̎�|�i�����̉��ɃN���t�g����������܂����B
�ޗ�����قǂ��������܂��������܂����̓��e�B
�搶�͂R�C�W�O�O�~
�s���}���ق֍s���P���̖{�������܂����B
�O���t�Ђ̃}�C���C�t�V���[�Y�u���U�[�N���t�g�v�i�F��a�q�ďC�j�R�C�W�O�O�~�ł����B
|
��i�a |
���߂Ă� |
�Z�J���h�o�b�O |
| �R�[�i�[�E���}�`�Ȃǂ̏��������{�Ƃ��� | |
|
���U�[�J�[�r���O�̖͗l�����{�ǂ���ł����A�Ȃ�ƂȂ��S�c�C�����Ŏg�p����C�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B |
|
�@
|
�H���T |
���U�[�J�[�r���O�͗l�̍��� |
���U�[�J�[�r���O�ɕK�v�ȓ���ƍޗ�
| �ޗ��̓^���j���Ȃ߂��̋��v �v�̓^���j���Ȃ߂��̋��v��p���܂��B |
�����͂S��� �Œጻ���K�v�ȓ���͐n����]���ĂȂ߂炩�ȃJ�b�g�� �ł���u�X�[�x���J�b�^�[�v�ƍ���H��E�ؒƁE�S���ł��B |
|
�S�̖_�̐�ɖ͗l�����܂ꂽ���{�̍���H�� |
�n����]���ĂȂ߂炩�ȃJ�b�g���ł���u�X�[�x���J�b�^�[�v�@ |
���U�[�J�[�r���O�̊�b
|
���肽���}�Ă������܂� |
���Ŏ��点���a�v�ɒܗk�}�Ȃǂň��t���܂� |
�X�[�x���J�b�^�[�œK�� |
|
|
�X�[�x���J�b�^�[�Ő؍��݂� |
�����̍���i�X�^���s���O�j�H�� |
�X�^���s����H��̎��
�x�x���iBevelers�j�A�x���i�[�iVeiners�j�A�J���t���[�W���iCamouflage�j�A�y�A�V�F�_�[�iPearShaders�j
�V�[�_�[�iEeders�j�ȂǂW��ނP�O�O�{�ȏ�̍H�����܂��B
�S��������Ɛ����~�K�v�ł��̂Ŋ�{�I�Ȃ��̂��P��ނW�{���x������Ƃ����ł��傤�B
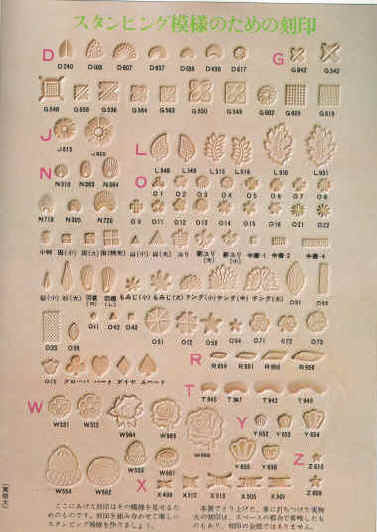
|
�悭�g���X�^���s���O�H��́A���̒��̐��{�����ł��B |
|
���̑��悭�g������͎���̍H��܂ɓ���Ă��܂� |
|
��D���̐j���ł� |
�v��|�ޗ����X�u�N���t�g�Ёv
�����̍H���ޗ��͒n���s�s�ł͓��肵��Ȃ�A�S���ł����Ђ�������܂���B
���̒��ŒʐM�̔����œ��肵�₷���̂��u�N���t�g�Ђł��B
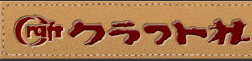
�d�b�ԍ���03-5698-5511�@FAX03-5698-5533�@
�C���^�[�l�b�g��http://www.craftsha.co.jp/
��167-0051�@�����s�����扬�E5-16-21
|
��i�b |
���߂Ẵl�[������ |
�͂��݃P�[�X |
 |
|
|
�I���W�i���Ȗ��O�����i |
|
 |
|
�傫�ȕ����́u�A���t�@�x�b�g����Z�b�g�v�i5,000�~�j |
|
�A���t�@�x�b�g����_�Z�b�g�i�V�C�T�O�O�~�j |
��������_�Z�b�g�i�Q�C�T�O�O�~�j |
����Z�b�g�͍����悤�ł����Q�S�N�O�ɍw�����Č��݂��ς�炸�g���Ă܂��̂ŕ֗��ň����������Ǝv���Ă��܂��B
|
��i�c |
���U�[�J�[�r���O |
�ʋo�b�O |
| �@ | �@ |
| �@ | �@ |
�@
|
�H���U |
�^�� |
|
���������`�̍�i�͍��E�Ώ̂���� |
�傫�����P��������Ă��Ԃ̔������傫���ɂȂ�̂� |
�@
|
��i�d |
�T�����T�C�Y |
�s�l�C�w���J�o�� |
|
�ō��̊v�Ǝ�ԂЂ܂��Ƃ�ʎ���o�b�O |
�����f�U�C���̍��z�ƒ��������t�� |
|
�D�����ō� |
�|�P�b�g�Ȃǂ��ӂ�� |
�@
|
��i�e |
|
��܂���z |
|
��܂���z |
|
�@
|
�H���V |
���� |
�����E�痿�͂Q�R��ނ��̍ޗ����p�ӂ���Ă��܂��B
����
�@�N���t�g���U�[�����F�@�^���j���Ȃ߂��v�ɂ悭���߂��A�������N���ȐF���o���܂��B
�A�v�`�����F�@�^���j���Ȃ߂��v�A�N���[���Ȃ߂��v�A������v�Ȃǂɂ悭���߂��܂��B
�B���U�[�_�C�F�@������������ƐZ���͂���������ɋ����A���R�[���n�̐�����
������c�J�[�r���O�悤�̐����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�C�I���K�_�C�F�@�B�Ɠ����e�ʂŎg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�D���U�[�����F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�E��������F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�F�A���R�[�������F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�G�A���e�C�b�N�t�B�j�b�V���F�@�g�������Ƃ�����܂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�H�痿�F�@�v�p�̊G�̋�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�I�X�p�^�[�C���N�F�@�o�b�N�O�����h�̕����ɐF�������̂Ɏg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�⏕�ޗ�
�J�Ƃ����t�F�@����������n�����̂Ɏg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�K�����߉t�F�@�v�`��������U�[�_�C����������ɉ����ނ�Ȃ��d�グ��̂ɂ����܂�
�L���L�|�_�F�@���U�[�����A��������Ɏg���Ƃނ�Ȃ����܂�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�M���W���[���F�@�痿�ɍ����g���܂��B��o���p�Ƃ�����p������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@
�N�Z���܁F�@���߂��̈����v�Ɏg���Ɨǂ����܂�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�d�グ��
�O���U�[���b�N�X�F�@���t��̂�o���܂ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ȂǂȂǂ�����܂��B
|
���n���������ꍇ |
���F�����Ɏd�グ���ꍇ�A�����o�ɂ�ē����ɂ₯�ăA���F�ɂȂ�v�{���̎��R�̖��킢���o�Ă��܂��B
�L���u�����h���̃��C�r�g���o�b�O�ɂ����̎�@���g���Ă��܂��B
|
���̏ꍇ�o�b�N�O�����h������ |
��Ȃ��Ƃ̓o�b�N�O�����h����F�� |
|
�@
|
�n���� |
�v�S�̂���߂���@�ł��B
�v�S�̂����������߂�͓̂�����Ƃł��B
����ɂ͊v�S�̂����������߃X�|���W�ȂǂŎ��点�܂��B
���点��őS�̂̐F���Z���Ȃ����蔖���Ȃ����肵�܂������ꂪ����̂����Ƃ���ł��B
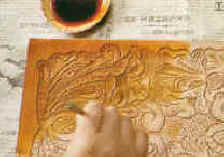
|
�A���e�B�b�N���� |
�J�[�r���O�̉����ɐ������c���A�e��t���Đ��߂���@�ł��B
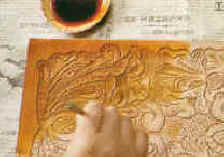 |
 |
 |
 |
| �n���߂Ɠ������@�Ŋv�S�̂���߂܂��B | �y�[�X�g��̃A���e�B�b�N�t�B�j�b�V�����悭���������A���������Ă���v�̏�Ƀu���V�Ȃǂł����Ղ�Ƃ̂��܂��B | �n���Ȃǂʼn������ɓ���悤�ɉ����܂��B | �悭�����Ă���d�グ�܂�h��܂��B |
�@
|
�x���g��1�{�v�ŃA���؊v���t�� |
�ł����q�ɂ͕s�l�C�A��x���g��ꂸ�ߏ��̒m�l�ɂ�����Ă����܂����B
|
�H���W |
��D�����@ |
�~�V���D������v�Ȃ킯
�@�F��D����i����������Ƃ��d�オ�蒷��������͖̂D���ڂ̓~�V���D���Ǝ��Ă��܂����A�㎅�Ɖ����̋�ʂ�����
��Ɖ��̎����D���ڂŌ��݂ɓ���ւ��A�~�V���D���̂悤�Ɏ����r���Őꂽ�ꍇ�ق�Ă��邱�Ƃ�����܂���B
�A�F�D�����ɖD�������g���ċ��鎞�ɂ���Ȃ��悤�Ɋv�ɍa��t���ĖD���ڂ߂܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�B�F�D�����ɂ͘X�������A�������ؖȎ����g���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| �@���{�ł̓X�e�b�`���O�O���[�o�[�Ŋv�̃w���ɍa���Ƃ���܂����A�� | �����͊v���キ�Ȃ�̂�h�����ߊv�𐅂ŏ_�炩�����ăw�������ōa��[���t���D������t���鎖�ɂ��Ă��܂��B |
| �@���{�ɂ͊v�p�H��̃X�e�b�`�����b�g�i�P�D�Q�O�O�~�j �ōa�̒��ɖD���ڂ̊Ԋu�̈�t��������Ƃ���܂��B |
�����̂����F�m�ٗp�̃����b�g�ň��t���܂��B |
�D�����͊v�Q�����ꏏ�ɂ����܂��B
| �@���{�͍�Ɨp�S���Ɋv��u���Ђ��ڑł��̐n���a�ɕ��s�Ɏ����Ĉ�̏�ɓ��āA�ؒƂőł��ĂЂ��`�̌��������܂� | �@�����̂����́u�Ђ��ڑł��̐n�v�ł͌����傫�����ėm�ٗp�̃����b�g�Ԋu�ł͌����Ȃ����Ă��܂��܂��B �@���̂��߁u�Ђ�����v���g����̕��ʼn������Ē@���Č��������܂��B |
�D���j�͖ؖȐj�̐�𗎂Ƃ����ۂ���̐j
| �@�D�����̒����͂P���܂� �D�����̗��[�ɐj��t���܂��B �������͏�̎ʐ^�̂悤�ɂ��ė��[�ɌŒ肵�܂��� �ׂ����̓{���h�ȂǂŐڒ����܂��B �������Pm�̗��R�͉��̗��R�ɂ��܂��B |
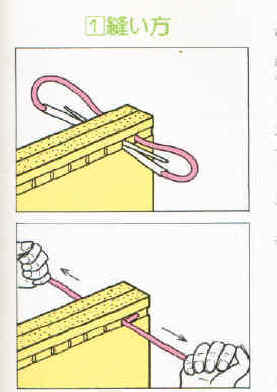 |
|
| �P���̎��ŖD����͖̂�R�O���� �D�����͏�̐}�̂悤�ɖD���n�߂��玅�����݂ɒʂ��āA �������߂Ď����̌��i�݂܂��B ���̂Ƃ�������������Ǝ������܂��Ď����i�ނ̂Ɏ��Ԃ��|����܂��B �܂��A���x���D������ʂ��Ă���ƃ��E��h���Ċ���₷�����Ă��Ă� �����ׂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B ���̂��ߎ��̒����͂P�����x�܂łƂ��܂�����R�Ocm�����D���i�߂܂���B �i���͖D���ڂ̖�R�{�K�v�ł��j |
|
�@
|
��i�f |
���߂Ă̂����� |
�Z�J���h�o�b�O |
�̊v�荇�킹�邽�߂ɊȒP�ȁu����������v�i�E�B�b�v�X�X�e�b�`�j�Ŏd�グ����i�ł��B
|
�H���X |
������ |
�v��i�̎d�グ�ɂ́A��r�I�ȒP�ɏo����u������v�d�グ���ǂ��g���܂��B
�u������v�Ƃ́A�̊v�Ɍ��������A�v���[�X�i�v�Ђ��j�Ōq�����킹�Ă������Ƃł��B
|
������ɂ͂����ȕ��@������܂� |
�d�オ�肪���Ɍ�����u�_�u���X�e�b�`�v |
�Y��Ɏd�グ��ɂ�
�̊v������Ȃ��悤�ɁA���m�Ȃ����茊��������K�v������܂��B
�����꒼����A���Ԋu�ɕ��Ԃ悤�ɂ��܂��B
����͂R��ނ���܂��B
�i���j�F���Ԋu�Ɉ�������ʒu�Ƀp���`�Ō�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
(���j�F�O�{�ڑł��Ő��m�Ɍ��������܂��B�Ȃ��蕔���͈�{�ڑł���p���Y��ɃJ�[�u�����܂��B
�i�E�j�F�t���[�����X�X�e�b�`�ŕ��L�v���[�X���g���ꍇ�̓n�g���ł����茊�������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@
���[�X�j
���[�X�j��2��ނ���܂��B
�v���[�X�̐���Ă�1cm�𔖂������A�j�̓����J���Ă͂��݂܂��B
|
���[�X�����ɒʂ��Ē܂Ŏ~�߂܂� |
2�{�̒܂Ŏ~�߂܂��B |
�@
|
�H���X-1 |
�ȒP�Ȃ����� |
|
�z��D���v�̂Ɠ����ł��B |
���������Đj�����A��������� |
����������Ƃ������܂��B |
�@
|
�H���X-2 |
�t���[�����X�X�e�b�` |
�\�t�g�Ȋ����̃X�e�b�`�ł��B
�����L���ď_�炩���R���g���܂��B
���������R���������d�˂āA�v�̍ق��ڂ������Ȃ��悤�ɂ��܂��B
|
�����n�߂͐ڒ��܂�t����d�Ɋ����Ă��玟���̌��i�݂܂��B |
�I��͕R���x�ʂ��Ă��痠�ɏo�� |
|
�@
|
�H���X-3 |
�V���O���X�e�b�` |
�����钷����5�{
�V���O���X�e�b�`�ɕK�v�Ȑ샌�[�X�̒����́u������v��������T�{�ł��B
50cm�̒�����������ɂ���Q�D�T���̊v���[�X���K�v�ł��B
|
�V���O���X�e�b�`���_�u���X�e�b�`�� |
�V���O���X�e�b�`�̏ꍇ�� |
|
�Ō�̎n���̎d��
�r�����炩����n�߂�1�����Č��̈ʒu�ɖ߂������̍Ō�̎n���̎d���ł��B
|
�r������̂�����n�� |
�܂��A�v���[�X�̎n�߂̒[�� |
|
���̗ւɂP�������v���[�X��ʂ��A���̂܂܁A�ŏ��̌��ɐj�����A�v�̊Ԃɒ[�������o���Ďn�����܂��B |
||
| �P������������I��� | |
�@
|
��i�g |
�iS56�N1981�N�j |
�e�j�X���P�b�g |
�_�u���X�e�b�`�Ŏd�グ���e�j�X���P�b�g
�����钷������P���W�O�����B
������v���[�X���P�S���K�v�ł��B
�v���[�X�ゾ���ł�16,000�~�i�P�S���j
|
�H���X-�S |
�_�u���X�e�b�` |
�����钷�����W�{
�V���O���X�e�b�`�ɕK�v�Ȑ샌�[�X�̒����́u������v��������W�{�ł��B
50cm�̒�����������ɂ���S�D�O���̊v���[�X���K�v�ł��B
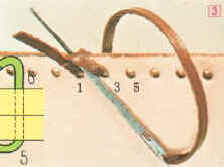 |
||
|
�V���O���X�e�b�`���_�u���X�e�b�`�� |
�_�u���X�e�b�`�̏ꍇ�� |
|
�Ō�̎n���̎d��
�r�����炩����n�߂�1�����Č��̈ʒu�ɖ߂������̍Ō�̎n���̎d���ł��B
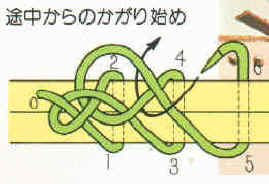 |
|
|
�V���O���X�e�b�`�� |
�_�u���X�e�b�`�� |
 |
 |
|
�܂��A�v���[�X�̎n�߂̒[���P���͂����Ċv�̊Ԃɓ���āA |
|
 |
 |
 |
|
���̗ւɂP�������v���[�X��ʂ��A���̂܂܁A�ŏ��̌��ɐj�����A�v�̊Ԃɒ[�������o���Ďn�����܂��B |
||
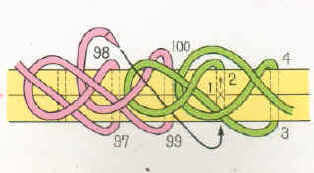 |
 |
| �P������������I��� | |
| �𑧂�����c��w�����o�ϊw���ɓ��w�����̂��L�O���č��܂����B �̂��Ƀf�J���P�����s���Ďg���Ȃ��Ȃ�܂����B |
|
| ���P�b�g�ޗ����Q�T,000�~���i���쎞�Ԃ͖�40���Ԋ|����܂����B����700�~�Ōv�Z�����2��8��~�B�j���v�T���~ | |
�@
| �����ȃA�C�e���ɒ��� |
�͂��݃P�[�X�A�y���P�[�X�A��܂���z�A���K����A�|�V�F�b�g�A�L�[�z���_�[�A���������
���h����A���C���R�[�X�^�[�A�ȂǂȂǏ����͐�����Ȃ��쐬���܂����B
|
��i�� |
���K����|�V�F�b�g |
|
�傫���͕��P�Ocm�~�����Vcm |
|
�@
|
��i�� |
�l�[�����菬�K���� |
| �q���͂���قNJ�т܂���ł�������l�͑����g���Ă���܂����B | |
�@
|
��i�� |
��������� |
|
��\�N�g���Ă��v�̓z�`���Ȃ��I |
|
��i�� |
������w�w���ؓ��� |
| �𑧂����̂�������w�A�o�ϊw���ɓ��w�ł�����̃C�`���E�}�[�N����̊w���ؓ��������Ă��܂����B �w���͒�������傫���̂ŋɗ͏��������邽�ߖD����C�b�p�C�܂Ŋv���l�߂܂������������v�͏�v�łS�N�Ԏg���Ă� ���v�ł����B |
|
|
��i�� |
���̃A�C�e�� |
|
�n�T�~�P�[�X |
���v���y���_���g |
�u���y������ |
| ���v�i�o�b�N�X�L���j���y���P�[�X ���ł��g���Ă��܂��B |
|
|
�傫���������K���� |
|
�㔼�֑��� |